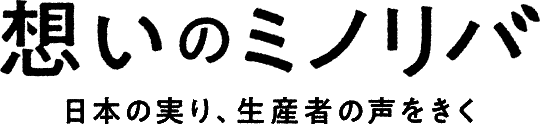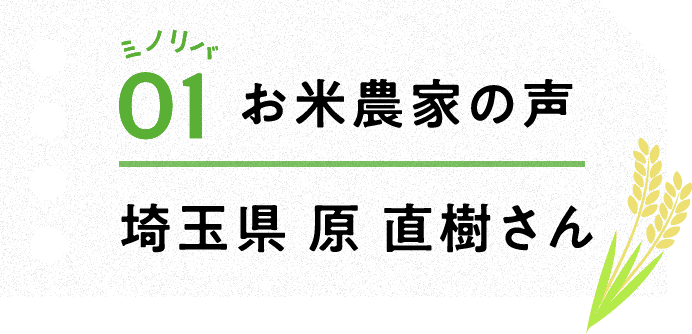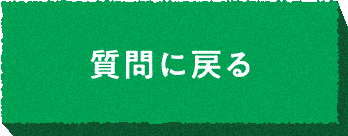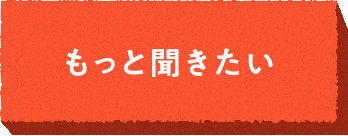米づくりへのこだわりを
聞かせてください!
米づくりへのこだわり
今、私のところでは、40ha(ヘクタール)の圃場で4品種の米を生産しています。中でもコシヒカリとミルキークイーンのブレンド米は、お客さんから好評で、そのおいしさにはちょっと自信があります。ミルキークイーンにはお米ともち米の中間的な性質があって、これをコシヒカリとバランスよく混ぜると、日本人好みの絶妙な旨みと甘み、そして粘りが生まれます。

炊き立てはもちろんですが、冷めてもおいしいので、おにぎりやお弁当にもお勧めですね。この品質と収量を保つには、毎日の弛みない努力が必要です。米作りは田植えをしたら終わりでなく、そこからが始まりです。中でも特に重要なのは、田んぼの水管理だと考えています。

作付したすべての圃場に毎日欠かさず足を運び、稲が育ちやすい環境になるよう生産者としてできる手助けをしています。とても大変ですが、やったこと、やらなかったことの答えは必ず収穫時に返ってくるので、やるしかないですね。
米づくりへのこだわりを
聞かせてください!
こだわり続けたい!
だけど環境が…
収穫時に後悔したくないから、今できるだけのことをする。その覚悟はできているのですが、正直、どうにもならないこともあります。たとえば、高温障害。温暖化による平均気温の上昇によって、米の品質も収量も大きく低下しているのです。高温への耐性を持つ品種も取り入れてはいますが、

高温障害対策はどの品種でも大変です。穂を出す時期に高温になると障害が発生しやすいため、田んぼの適切な水管理など対策に取り組んでいますが、最近の環境は稲が育つにあたってとても過酷になっていますね。少しでも暑さが和らげばいいですが、近年は厳しさが増すばかりなので、暑さに負けない米作りに挑み続けたいですね。

よい収穫を迎えるための
努力とは?
よい収穫を迎えるために
品質・収量ともに満足できる収穫を得るために、簡単な秘訣や近道はありません。やはり、日々の弛まぬ努力が必要です。水の管理以外にも、肥料や農薬の散布などさまざまな面で、つねに課題が突きつけられますから。中でも今、最も頭を悩ませるのはイネカメムシですね。近年の気温上昇によって越冬するイネカメムシが増え、

出穂期を迎える7月頃から田んぼに大量に飛来してきます。イネカメムシは、デンプンが溜まった乳熟期の穂を吸汁し、品質や収量の低下を引き起こします。そのため、出穂期に防除することが重要です。昨年は動噴(動力噴霧器)を使い一部圃場の防除を行いましたが、日中の猛烈な暑さや他の作業が重なる時期でしたので、

残りの圃場はJAのドローン散布サービスを活用しました。今年はドローン散布サービスの活用を全面積に広げるなど、スマート農業技術も積極的に取り入れ、よい収穫が迎えられるよう準備を進めています。
よい収穫を迎えるための
努力とは?
努力は惜しまない!
だけどコストが…
よい収穫のための努力は、尽きることがありません。しかし、何をするにもコストがかかります。近年の燃料費の高止まりは物流コストの上昇につながり、あらゆる農業生産資材の価格に上乗せされていますので、今は何もかもが高騰しています。輸入原料の割合が多い肥料は、特に価格の上昇が激しいですね。

農薬は地域で共同購入するなどの工夫をして、多少は負担を抑えることができていますが、単価自体は上がり続けている状況です。ドローン散布など、スマート農業技術を取り入れるうえでもコストはかかります。コストを抑える努力は日々重ねていますが、それも限りがあります。

米の価格高騰が話題となっていますが、今回を契機に消費者と生産者がともに納得した再生産可能な価格で取引されるようになることを願うばかりです。
これからの農業への
想いをどうぞ!
これからの農業への想い
今、全国的に農業の担い手が減っていますよね。このまま農業を続けていくことができるか不安になるときがあります。でも、私は地域の仲間たちと一緒に農業を続け、農地を守っていきたい。私の地域も離農者が増えるなか、新たな担い手はいないので、農地を維持していくのに悩みを抱えています。

将来にわたって農地を守っていくには、米以外の作物である麦や大豆などの作付けも組み合わせて、作業分散や収益性を高めることを考えなくてはなりません。そのためには、地域の合意を得て水路を止め、麦や大豆を栽培できる地域づくりが必要になります。

地域を支える行政・JA・地権者・担い手の4者で話し合いながら、農地利用の将来像を描く「地域計画」を高い完成度でつくっていくことが重要になりますね。近年、車で走っていると、目に入る耕作放棄地は年々広がっているのを感じます。そうなる前に、地域全体で農業を守っていかなければなりません。私たち担い手が先頭に立って、みんなで持続可能な農業環境をつくり、次の世代が「やってみたい」と思える職業にしていきたい。それが私の「これからの農業への想い」です。
これからの農業への
想いをどうぞ!
これからを担っていく!
かけられるだけ手をかけて、品質・収量ともに納得できる米づくりを行う。しかし、手をかけるにも限界はあり、何にどこまでこだわるか、日々その裁量が問われるのですが、答えは収穫時までわかりません。また、自然が相手ですから、手をかけた分の見返りを得られないこともあります。

そこに農業の難しさが詰まっていますが、たらればの後悔はしたくないので、自分が納得できるまで手をかけています。私には大学生の息子がいますが、本人の意思を尊重したいので、私から「農家を継いでくれ」とは言わないでしょう。しかし、私をはじめ多くの農業者がひたむきに働き、充実した生活を送る姿で、

息子のような次の世代が「農業」という職業に憧れを持つようにしたいのです。そのために、「もう少し頑張ってみよう」という気持ちを支えるのは、自分が育てた米を選んで、食べてくださる方々です。これからも、もっとたくさん味わっていただきたい。そのための努力は、これからも惜しまず続けていきます。