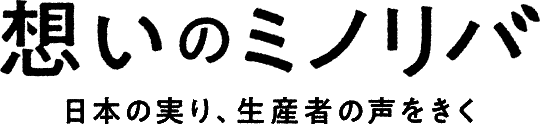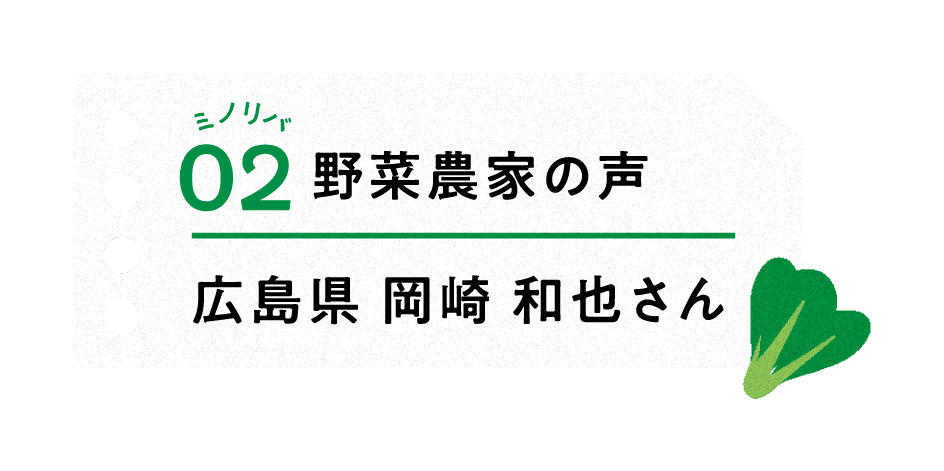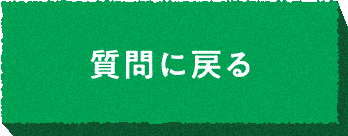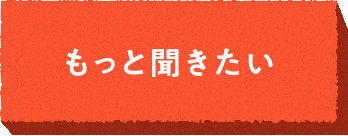野菜づくりとの出会いを
教えてください!
野菜づくりとの出会い
高校卒業後、私はJ2のサッカーチームに入団し、プロ選手として6年間活動しました。24歳で引退、セカンドキャリアとして漠然と「尊敬できる仕事を」と考えていたなか、私を農業へ導いたのは、現役時代から通うイタリアンのお店でした。日々、色とりどりの野菜が届けられ、ショーケースで輝く光景を目にするなか、毎日新鮮な野菜を届け続ける農家の仕事に尊敬を覚えたのです。

私の実家は米をつくる兼業農家で、小さいころに田植えや稲刈りを手伝った経験から、農業は身近な存在でした。引退して間もなく、地元広島で自治体の研修を受けて、27歳で新規就農。現在は、45aの施設(ビニールハウス)と50aの路地で、ミニトマトと小松菜をはじめとした10品目の葉野菜を栽培しています。

野菜は、その品種や生育環境などによって向き合い方が変わるため、常に考え、学び続けることが大切です。そこは、私の性格に合っているなと感じます。サッカーで司令塔をやっていたので、視野広く細かなところまで目が届きますし、考えながら動く習慣も染みついています。時々、サッカーをしていたころの感覚が蘇ってきますね。
野菜づくりとの出会いを
教えてください!
野菜づくりは楽しい!
だけど苦労も…
イタリアンのお店で、野菜の美しさに目を奪われ、おいしさに心を動かされた当時の記憶。現在の仕事の原点はそこにあるため、栽培する野菜の品質にはこだわりを持っています。しかし、想像以上の苦労に心が折れそうになることもあります。特に苦労しているのは、年々厳しさを増す「暑さ」への対策です。

空調設備で施設内の温度を常に制御できれば良いですが、コストを考えるとそういうわけにはいきません。施設の上に遮熱用の資材を張ったり、水やりを工夫したり、植物本来の力を引き出すバイオスティミュラント資材を使って暑さへの耐性を高めるなど、高品質な野菜を栽培できるよう試行錯誤しています。

野菜の生育環境は地域の勉強会でもよく議論します。様々な人から情報を入手し、自身の失敗は糧にしながら、毎年の積み重ねで対応していくしかないですね。
品質への
こだわりとは?
品質へのこだわり
私が農業を営む広島県阿戸町は、綺麗な水や豊かな土壌に恵まれ、安全・安心でおいしい野菜を栽培するには申し分ない環境です。土にもこだわり、就農当初から地域の畜産農家と連携して堆肥を活用し、良い土づくりができるよう心がけています。

JA全農ひろしまでは、畜産農家から生まれる堆肥を資源として再利用するなど、資源循環型農業で生産された農畜産物・加工品を「3-R*」というブランドで販売されています。
畜産堆肥を活用しながら、こだわった土で栽培した高品質な野菜を、JAグループとも連携して消費者にお届けし、自身の農業経営も安定させていきたいと思います。

*「3-R」とは「耕畜連携」による資源循環型農業で生産された農畜産物や加工品のブランド。畜産業で出た堆肥を「資源(肥料)」(Resource)として「再利用」(Recycling)する資源循環・構築連携の取り組みを「繰り返し」(Repeat)ていくことで、地域の環境保全と持続可能な農業を目指している。
品質への
こだわりとは?
求められているものをつくりたい!
でも現状は…
野菜づくりには品質へのこだわりに加え、求められるものをつくるといった視点も大切です。
市場に一斉出荷される野菜の価格は、需要と供給のバランスで決定しますが、野菜の多くは長期の保管ができないため、ひとたび供給過多となると値崩れが起こり、経営にも影響があります。

しかし、地域単位で求められる野菜の量や各生産者が生産する量がわかるようになれば、生産者間の調整に活用でき、計画的な生産も可能になるのではないかと思っています。
需要と供給のバランスを保つことは、生産者のみならず、消費者にとっても納得できる適正価格の形成につながります。

広島県内で食べられる野菜は広島県内で生産する、いわゆる「地産地消」を強化していきたいですね。
これからの農業への
想いをどうぞ!
これからの農業への想い
私の農園では従業員とパートのスタッフ10名程度で運営しながら、農繁期には近隣大学の学生にも手伝ってもらっています。幸い、自身の農園では人手を確保できていますが、農業界の人手不足は深刻です。

人手不足の問題解決として、先進技術を活用した省力化はよく耳にしますが、経営を成り立たせるうえでは、費用対効果を見極める必要があります。
また、私が農業を営む地域は中山間地のため、土地の集約には課題があり、規模の拡大も一筋縄とはいきません。

課題は積み重なっていますが、ひとつひとつ立ち向かって、自身の農業経営を発展させていきたいと思っています。
これからの農業への
想いをどうぞ!
地域農業を盛り上げたい!
「消費者から求められる、おいしい野菜をたくさんつくって地域農業を盛り上げよう!」というのが私の想いで、近隣の生産者とはその想いをいつも語り合っています。

私は就農当初から、農業に興味を持つ子どもを後押ししたい想いで、小学生・中学生の農業実習受け入れをおこなっていますが、成長した当時の学生からは「将来、農業をしてみたい」といった声をもらいます。

新規就農には大きな経済的負担がかかりますので、まずは私たちが彼らの受入先となり支援をしていきたい。しかし、受け入れるにも、任せるための土地を確保し、自身の経営規模を大きくしていくことが必要です。
土地の集約を進め、経営規模を拡大することは簡単ではないですが、将来を担う若者が就農できる環境をつくるべく、一歩ずつ取り組みを進めています。