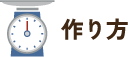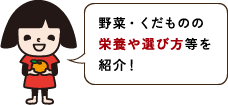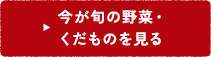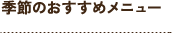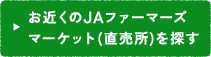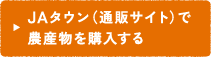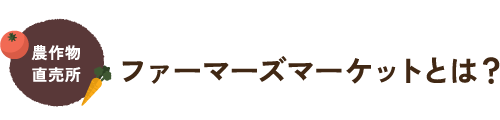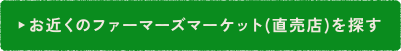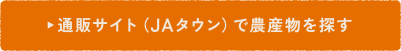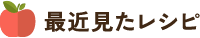長野県「手打ちそば」JA上伊那生活部会 箕輪町支所
行者の役小角が駒ケ岳に登る折、村人が大変親切にしてくれたのでそのお礼にそばの実と作り方を土産にしていったのが発祥と言われています。江戸時代高遠藩主だった保科正之公が後に会津にも根付かせました。春の花見や秋の新そばの時期にはイベントも開かれ、暮れには年越しそばとして根付いています。
材料(10人分)
| 〇そば粉 | 800g |
|---|---|
| 〇つなぎ(中力粉) | 200g |
| 〇打ち粉 | 適量 |
| 〇水 | 500㏄ |
| ※粉の42~45%位で状態等により量は変わる | |
じっくり!
お料理!
- <水回し>
そば鉢にそば粉とつなぎをふるい入れ混ぜ合わせ1~2回に分けて水を入れる。水(分量の90%位)を入れ、指先で円を描くように混ぜ合わせ生パン粉の状態にする。2回目は粉の状態をみながら水を少しずつ加える。生地をちぎって状態をみてひとまとめにする(生地の固さは耳たぶより少し固いぐらいが良い)。 - <練り>
体重をかけて押しつけながら練り込む。表面がしっとりつやが出てひびが出来なければ練り完了。力を入れず生地を少しづつ中心に向かって折り込む(折り込む作業を繰り返していくと中心に菊の花のような模様ができる(菊練り)) 。 - <へそ出し~くくり>
菊練りでできた「へそ」の部分を手前にし、中の空気を抜くように絞り込み、こね鉢のへりに沿って生地を回転させ円錐形にする。上から押さえて円盤状にする。 - <地延ばし>
のし板に打ち粉をふり生地をのせ、手の平で押しながらまわす。全体的に厚さ1cmにして、丸く伸ばす。 - <丸出し>
麵棒を手の平で押しつけながら、よりをかけるように転がす。ふちから落とさないように回転させ一周する。麺棒の持ち方を変えて転がし、一定の力で大きくし厚さ0.5cmの円形にする。 - <四つ出し>
四隅を出していく。生地の真ん中に縦に打ち粉をふり、麺棒に巻きつけ手前から奥に転がす。巻きとった部分が延びて「角が出る」。数回繰り返したら麺棒を180度回転して、手前から奥に広げる。広げたらまた手前から生地を巻きとり数回麺棒を転がして先に出した角と対角線に角を出す。 - <本延し>
四つ出しを終えた生地は角は薄く四辺の部分は厚い、この肉を移動し均一な厚さにする。中側の厚い所は肉分けする。あまり、力を入れ過ぎずに麺棒を転がし、全体を一定の厚さにして麺棒に巻く。 - <たたみ>
巻いた生地を縦にし、半分ほど広げ打ち粉を充分ふる。麺棒を持ち上げて打ち粉を振った生地に折り重なるように二つ折りにする。打ち粉をし、先端の生地をつかんで下の生地に重なるようにたたみ、四つ折りする。さらに八つ折りにする。右側の「わ」になっているところは揃える。 - <切り>
生地の下にも打ち粉をふる。小間板を左手で押さえ、包丁を小間板にあて上から奥へ包丁を押し出すように切る。切り分けたそばは空気にふれないようにラップをかけるか固く絞ったふきんをかけて、乾燥しないようにきをつける。 - <完成>
できるだけ大きな鍋にたっぷりのお湯を沸騰させる。打ち粉をふるい落としそばをほぐしながら入れる。一度沸騰したら麺が自分で泳ぐように火加減を調整する。
水回しはそばの味を決める重要な工程なので、丁寧に行ってください。 打ち粉は「延ばし」までは最小限にとどめ「たたみ」「切り」のときはしっかりする。

地元の農家が生産した採れたて農産物を
販売する、JAの直売所です。
生産者が、市場を通さずに直接農産物を販売する施設がファーマーズマーケット(農産物直売所)で、そのうちJAが運営しているものを「JAファーマーズマーケット」と呼んでいます。現在、全国で約1,700カ所のJAファーマーズマーケットがあり、道の駅内での開設や、カフェやレストラン、市民農園を併設する店舗も増えていて、観光スポットとしても注目を集めています。毎朝、地元の生産者から届けられた採れたての野菜や果物が並ぶファーマーズマーケットでは、作り手の顔が見える、安全で安心な旬の農産物を手に入れることができます。家族みんなで楽しめるワクワクスポットに、ぜひ足を運んでみてください!